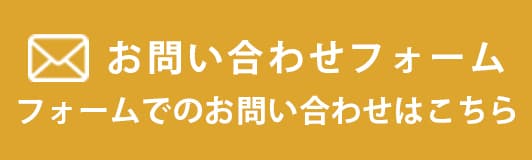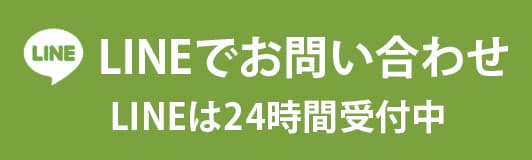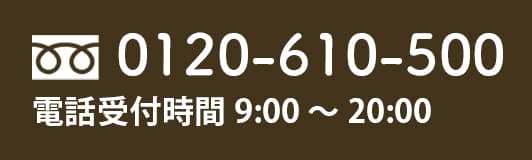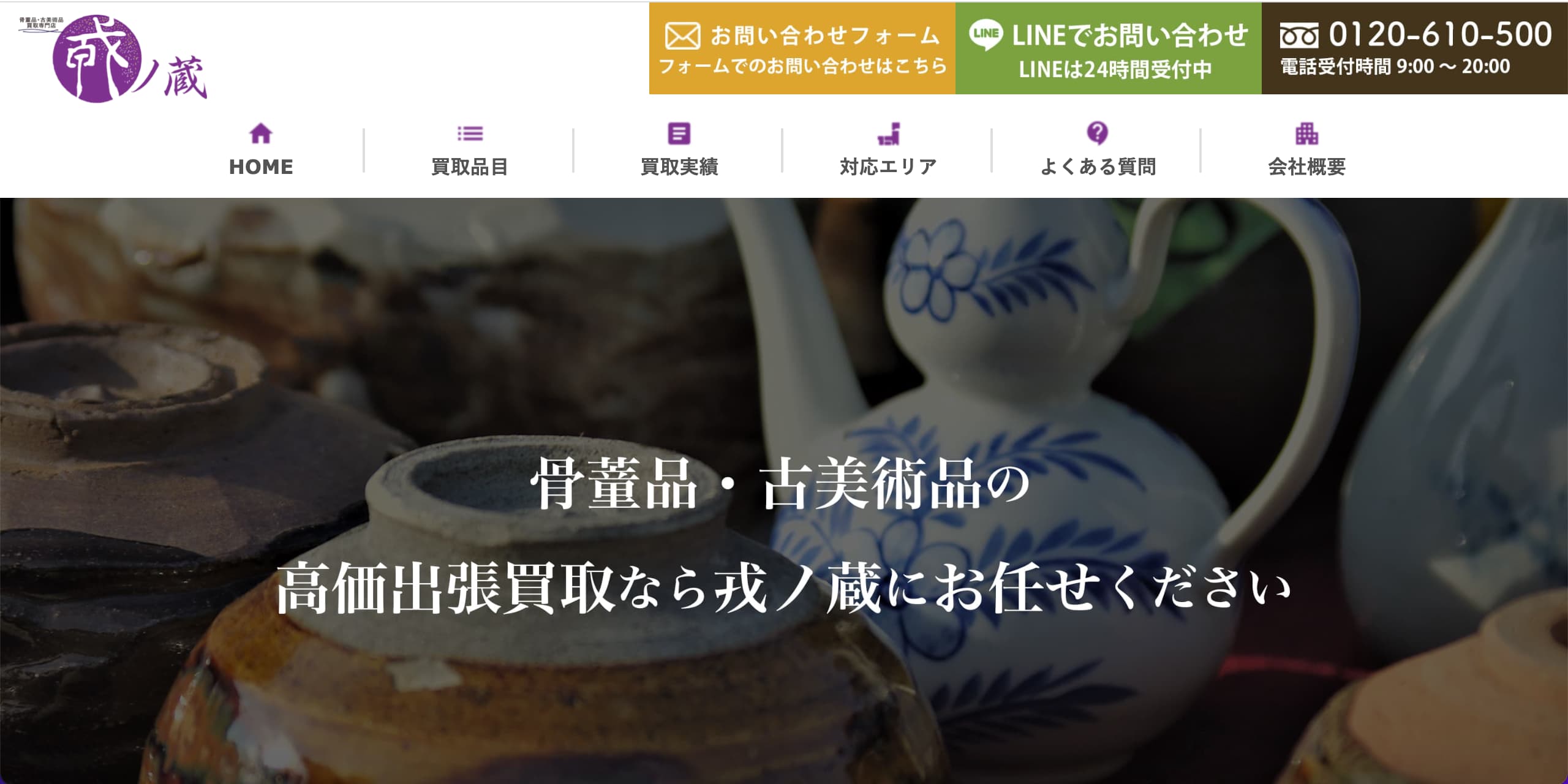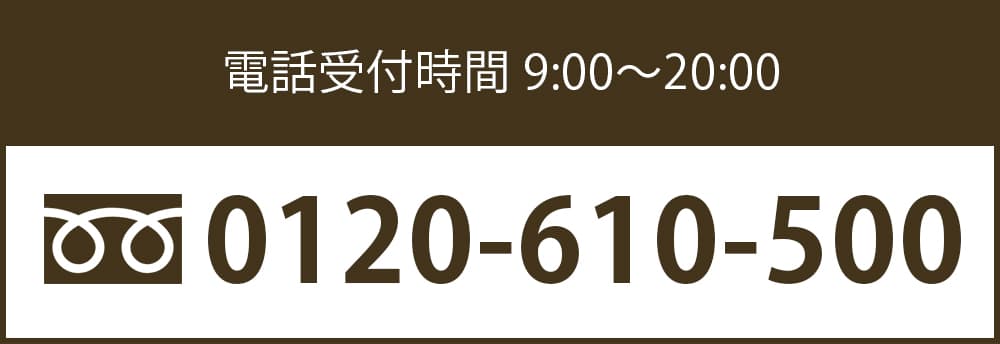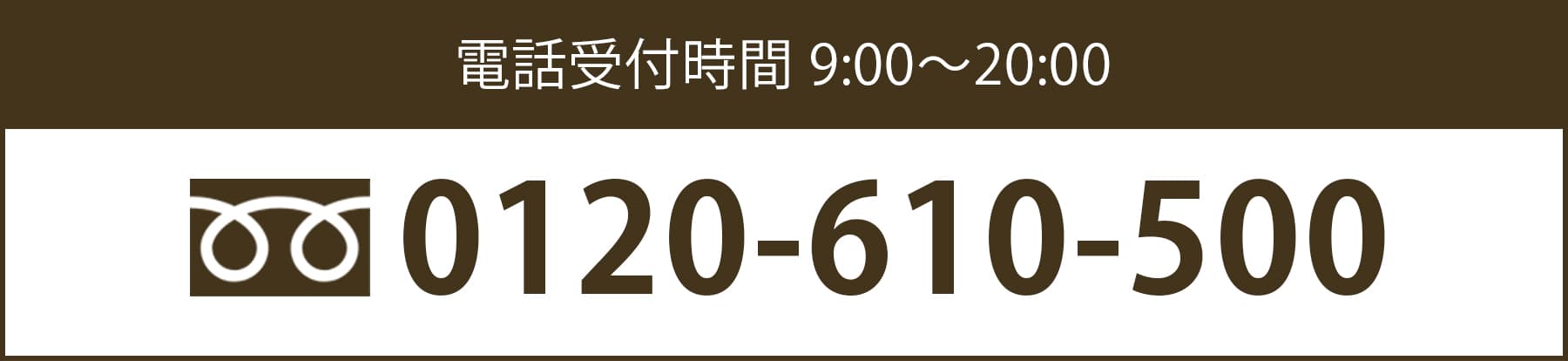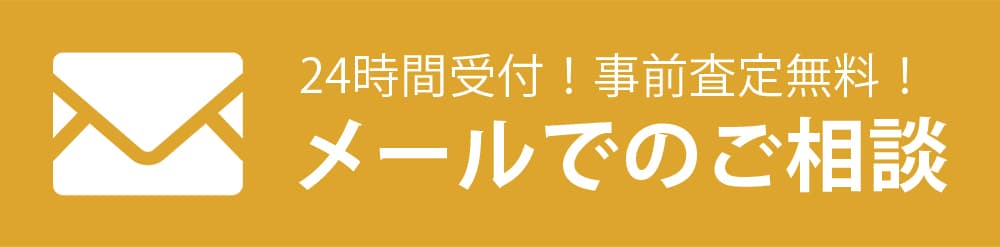【九谷焼と伊万里焼の魅力とは?】歴史・特徴・最新の買取相場を徹底解説
2025.11.09
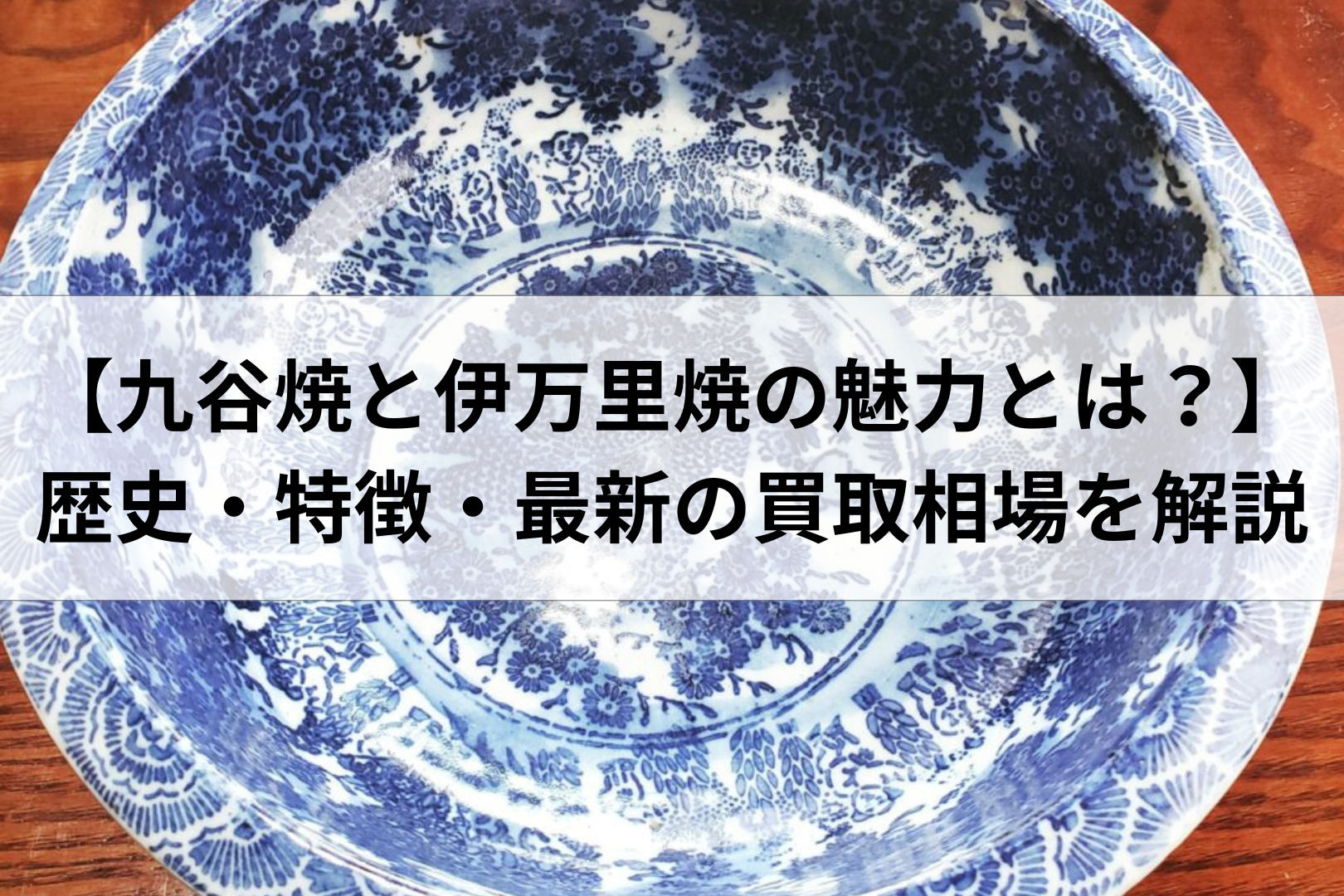
大切に保管してきた焼き物を手放す際の参考にしてみてください。
九谷焼と伊万里焼とは?

日本の伝統工芸品の中でも、特に世界的に高く評価されているのが「九谷焼」と「伊万里焼」です。
いずれも焼き物という共通点を持ちながら、その歴史や特徴、デザイン性には大きな違いがあります。
コレクターや美術愛好家から高い人気を誇り、近年は海外のオークション市場でも注目を集めています。
ここではまず、それぞれの焼き物の基本的な概要について整理してみましょう。
九谷焼とは
九谷焼(くたにやき)は、石川県加賀地方で作られる色絵磁器です。
大きな特徴は、豪華で鮮やかな上絵付け。赤・青・緑・紫・黄といった色彩を用いた装飾性の高いデザインは「ジャパン・クタニ」と呼ばれ、19世紀以降ヨーロッパでも人気を博しました。
実用的な器としてだけでなく、美術品としての評価が高く、飾って楽しむために収集する人も多いのが特徴です。
伊万里焼とは
一方、伊万里焼(いまりやき)は佐賀県有田を中心に生産された磁器の総称です。
「伊万里」の名は、海外へ輸出する際に伊万里港から船積みされたことに由来します。
日本で最初に誕生した磁器として知られ、白地に藍色の染付を施した清楚なデザインから、金彩をあしらった豪華な絵付けまで、幅広い作風が存在します。
特に江戸時代の「古伊万里」は美術的価値が高く、現代でも市場で高値がつくことで有名です。
共通点と違い
両者に共通するのは、いずれも日本を代表する焼き物であり、芸術性と実用性を兼ね備えている点です。
しかし、その魅力は異なります。九谷焼は「色の美しさ」で魅せ、伊万里焼は「磁器の完成度と輸出文化」で評価されてきました。
歴史的にも、九谷焼は加賀藩の文化的背景のもとに発展し、伊万里焼は輸出を通じて世界の陶磁器文化に影響を与えたという違いがあります。
なぜ今、注目されるのか
近年は骨董品ブームや和のインテリア人気の高まりから、九谷焼や伊万里焼に再びスポットが当たっています。
特に海外では、日本の伝統工芸品を「美術品」として高く評価する傾向が強く、オークションで予想以上の価格で取引される事例も少なくありません。
国内でも、作家物や古い時代の作品は高額買取の対象となるため、資産価値のある工芸品として見直されています。
このように、九谷焼と伊万里焼は単なる日用品の器にとどまらず、日本の歴史や文化を映し出す存在です。
次章では、九谷焼がどのような歴史を経て現代まで受け継がれてきたのか、その魅力をさらに詳しく解説していきます。
九谷焼の歴史と特徴

九谷焼(くたにやき)は、石川県加賀地方で生まれた色絵磁器で、その鮮やかな発色と装飾性の高さから、日本を代表する陶磁器のひとつに数えられています。
江戸時代から続く伝統を持ち、現代に至るまで数多くの作家が独自の表現を追求してきました。
ここでは、その歴史と大きな特徴について詳しく見ていきましょう。
九谷焼の歴史
九谷焼の起源は17世紀、加賀藩が磁器生産を奨励したことにさかのぼります。
最初の九谷焼は「古九谷」と呼ばれ、豪快な筆致と大胆な色使いで知られています。
しかし、その制作はわずか半世紀ほどで一度途絶えてしまいました。
その後、江戸時代後期に加賀藩や大聖寺藩が復興させたことで再び広まり、現代に至るまで脈々と続いています。
特に明治時代には、輸出向けの「ジャパン・クタニ」がヨーロッパで高い評価を受けました。
西洋の人々にとって、赤や金を多用した豪華絢爛な九谷焼は強いインパクトを与え、日本の美術工芸品としての地位を確立したのです。
九谷焼の大きな特徴
九谷焼の最大の魅力は「色絵」の美しさにあります。赤・青・黄・紫・緑の五彩を中心にした絵付けは、華やかでありながらも品格を感じさせます。
また、模様は花鳥風月や山水、人物など多岐にわたり、時代や作家によって多彩な表現がなされてきました。
- 古九谷様式
力強く鮮やかな色彩と大柄なデザインが特徴。 - 吉田屋風
緑、黄、紫、紺青の四色を駆使し、落ち着いた雰囲気を演出。 - 飯田屋風
細かな描写と精密なデザインで人気を集めた様式。 - 明治以降の輸出九谷
金彩を多用した豪華な装飾が特徴で、ヨーロッパ市場で人気を博しました。
このように、時代ごとに異なる技法やデザインが発展してきたため、「九谷焼」と一口に言っても非常に多様性に富んでいます。
九谷焼の魅力と価値
九谷焼がコレクターや愛好家に人気なのは、単なる器としての実用性を超えた「芸術品」としての側面が強いからです。
壁に掛ける飾皿や、美術館に収蔵される大鉢など、その作品は観賞用として高い評価を得ています。
また、近代以降は人間国宝や著名作家が多数活躍しており、その作品は市場で高額取引されるケースも少なくありません。
さらに、現代の九谷焼は伝統を受け継ぎながらも、モダンなデザインやインテリア性を重視した作品も多く生み出されています。これにより、若い世代や海外の新しいファン層にも受け入れられ、国内外で再び注目度が高まっているのです。
九谷焼は「色絵の芸術」と呼ぶにふさわしい鮮やかさと、多彩な作風を持つ磁器です。
歴史の中で一度途絶えながらも復興し、現代に至るまで人々を魅了し続けてきました。
その独自の世界観と華やかさは、他の焼き物にはない大きな魅力であり、コレクションや美術品としての価値を高めています。
伊万里焼の歴史と特徴

伊万里焼(いまりやき)は、佐賀県有田を中心に生産された磁器の総称で、日本の磁器文化を代表する存在です。
江戸時代から明治期にかけて国内外で高い人気を誇り、特に「古伊万里」と呼ばれる初期の作品は、現在でも骨董品市場で高額取引される価値ある陶磁器として知られています。
その誕生から発展までの歴史と特徴を詳しく見ていきましょう。
伊万里焼の誕生
伊万里焼の歴史は、17世紀初頭にさかのぼります。
朝鮮から渡来した陶工・李参平が有田にて磁器の原料となる陶石を発見し、日本で初めて本格的な磁器生産が始まりました。
これが「有田焼」の起源であり、伊万里港から積み出されたことから「伊万里焼」と呼ばれるようになったのです。
当初の伊万里焼は、中国や朝鮮の陶磁器文化を模倣しながらも、日本独自の美意識を反映して発展しました。
素朴で力強い染付(青一色の絵付け)が特徴的で、後に華やかな赤絵や金襴手が加わり、多彩な作風へと広がっていきました。
古伊万里の魅力
江戸時代前期から中期にかけて作られた「古伊万里」は、コレクターの間で特に高く評価されています。
白磁の美しい肌に藍色の染付を施した器は清楚で上品、さらに赤・緑・金を使った装飾が施されたものは豪華で存在感があります。
- 初期伊万里
17世紀前半に作られた素朴でシンプルな磁器。 - 染付伊万里
白地に青の文様を描いた、落ち着いた美しさが特徴。 - 金襴手伊万里
赤絵と金彩をふんだんに使った華やかな様式で、輸出品としても人気。
これらの伊万里焼は、美術的価値が高く、現代でも骨董市場で高額査定の対象となっています。
輸出陶磁器としての伊万里焼
伊万里焼の大きな特徴は、その国際的な広がりにあります。
17世紀後半、中国の景徳鎮窯が一時衰退したことを受け、日本の伊万里焼がヨーロッパ市場に大量に輸出されました。
オランダ東インド会社を通じて「ジャパン・イマリ」と呼ばれた磁器は、西洋の王侯貴族や富裕層に愛され、宮殿や城館の装飾に使われるほどの人気を博しました。
ヨーロッパの貴族社会では、伊万里焼を飾ることがステータスシンボルとなり、その影響は後のマイセンやセーヴルといった西洋磁器の発展にもつながりました。
つまり、伊万里焼は日本国内だけでなく、世界の陶磁器文化の歴史を動かすほど大きな役割を果たしたのです。
伊万里焼の魅力と現代的評価
伊万里焼は、九谷焼のように華やかな色絵で魅せるものもありますが、その根底には「白磁の美しさ」と「染付の繊細さ」があります。
シンプルながら深みのあるデザインは時代を超えて愛され、現代のインテリアにもなじむことから再評価が進んでいます。
また、伊万里焼は実用性と芸術性を兼ね備えており、日常の器としても鑑賞用としても楽しめる点が大きな魅力です。
特に古伊万里は希少性が高く、保存状態の良い作品はコレクターにとって垂涎の的となっています。
伊万里焼は「日本初の磁器」としての歴史を持ち、国内外で愛され続けてきました。
古伊万里のシンプルな美しさから、豪華な金襴手まで、その多彩な作風は世界中の陶磁器ファンを魅了しています。
現在も市場で高い評価を受けており、文化的価値と資産的価値を兼ね備えた存在といえるでしょう。
九谷焼と伊万里焼の違い

九谷焼と伊万里焼は、どちらも日本を代表する陶磁器として世界に知られています。
ともに江戸時代から発展してきた歴史を持ちながら、その成り立ちやデザイン、そして評価されるポイントには大きな違いがあります。
ここでは、両者を比較しながら違いを明確にしていきましょう。
産地と背景の違い
まず大きな違いは産地です。
-
九谷焼
石川県加賀地方(加賀藩・大聖寺藩の庇護のもと発展) -
伊万里焼
佐賀県有田を中心に生産(伊万里港から輸出されたことから「伊万里焼」と呼ばれる)
九谷焼は地域文化や藩の美意識を反映した芸術性の高い焼き物であり、伊万里焼は海外輸出を通じて国際的に広がった焼き物といえます。
デザイン・絵付けの違い
両者の一番の違いは「見た目」に表れます。
-
九谷焼
赤・青・緑・黄・紫などを駆使した豪華な上絵付け。色彩豊かで大胆なデザインが特徴。観賞用としても人気が高い。 -
伊万里焼
白磁をベースにした染付(藍一色)や、赤絵・金襴手など多様な作風。比較的繊細で上品な印象を与える。
つまり、九谷焼は「色の芸術」、伊万里焼は「磁器の美と多様性」という言葉で表現できるでしょう。
歴史的背景の違い
九谷焼は一度途絶え、後に復興した歴史を持ちます。
そのため時代によって技法やデザインに大きな変化が見られ、多彩な作風が魅力です。
一方の伊万里焼は、誕生から一貫して磁器生産の中心を担い、輸出を通じて世界的な評価を確立しました。
特に古伊万里は、ヨーロッパでの人気によって美術史的にも大きな役割を果たしています。
評価されるポイントの違い
-
九谷焼
豪華な装飾性や作家の個性が強く、芸術作品としての価値が高い。美術館やコレクションに収蔵されることが多い。 -
伊万里焼
日本初の磁器としての歴史的価値と、海外市場での評価が高い。シンプルな染付から豪華な金襴手まで幅広く需要がある。
コレクターの間では、九谷焼は「華やかさを楽しむ」、伊万里焼は「歴史と実用性を楽しむ」という住み分けがされています。
海外での評価の違い
九谷焼は明治時代に「ジャパン・クタニ」として欧州で人気を集めましたが、その評価は芸術性に偏っています。
伊万里焼は17世紀から輸出され、「ジャパン・イマリ」としてヨーロッパの王侯貴族の間でステータスシンボルとなりました。
ヨーロッパの宮殿やコレクションに多く残っているのは伊万里焼であり、その国際的な影響力は九谷焼を上回ります。
九谷焼と伊万里焼は、同じ陶磁器でありながらも以下のような違いがあります。
-
九谷焼
石川の伝統、豪華な色絵、芸術的価値が中心 -
伊万里焼
佐賀の磁器、輸出による国際的評価、歴史的価値が中心
この違いを理解すると、それぞれの焼き物の魅力をより深く味わうことができるでしょう。
両者を比較して見ることで、日本の陶磁器文化の豊かさを実感できます。
コレクターが魅了される理由

九谷焼と伊万里焼は、日本国内のみならず世界中のコレクターを惹きつけてやみません。
その理由は単なる「古い焼き物だから」ではなく、歴史・芸術性・希少性が複雑に絡み合い、所有すること自体に大きな価値があるからです。
ここでは、コレクターが九谷焼と伊万里焼に強く魅了される理由を整理していきましょう。
1. 芸術的価値の高さ
まず大きな魅力は、美術品としての完成度です。
-
九谷焼
色絵の鮮やかさと大胆なデザインが特徴で、まるでキャンバスに描かれた絵画のような迫力があります。飾り皿や花瓶などは単なる日用品を超え、観賞用の芸術品として評価されます。 -
伊万里焼
白磁の美しさや染付の繊細さが光り、品格と落ち着きを感じさせます。金襴手など豪華な様式もありますが、根底には「磁器そのものの完成度」があります。
いずれも独自の美的世界を築き上げており、その芸術性に触れたコレクターは強い魅力を感じます。
歴史的背景とストーリー性
骨董品としての魅力は「物語」にもあります。
-
九谷焼は一度途絶えた後に復興したという歴史があり、各時代で異なる作風を楽しめます。古九谷の力強い筆致、吉田屋風の落ち着いた色調、明治期輸出九谷の豪華絢爛さなど、時代ごとの変遷を追う楽しみがあるのです。
-
伊万里焼は「日本初の磁器」として誕生し、オランダ東インド会社を通じてヨーロッパに渡った歴史を持ちます。王侯貴族の宮殿に飾られ、西洋磁器に影響を与えたという国際的なストーリーは他の焼き物にはない魅力です。
コレクターにとっては「一点の器が歩んできた道のり」そのものが価値であり、所有欲をかき立てます。
希少性と資産価値
市場で高額取引される背景には、希少性があります。
-
九谷焼の古作や著名作家の作品は、数が限られており市場に出るたびに注目を集めます。特に人間国宝の作品や明治期の輸出九谷は高額査定されやすい傾向があります。
-
伊万里焼の中でも「初期伊万里」や「古伊万里金襴手」は特に希少で、保存状態が良ければ数百万円以上で取引されるケースもあります。
美術的価値に加え、資産としての魅力もあるため、コレクターにとっては「持っていること自体が財産」となり得るのです。
海外需要の高まり
近年、海外市場での人気もコレクター心理を刺激しています。
欧米やアジアの美術愛好家の間では、九谷焼・伊万里焼は「ジャパンアート」として高く評価されています。
特に伊万里焼は西洋の陶磁器史と深い関わりがあるため、世界的に知名度が高く、オークションでも落札価格が上昇する傾向があります。
こうした国際的な需要の高まりは、「今のうちに集めておきたい」というコレクター心をくすぐる要因となっています。
実用性と美術性の融合
最後に見逃せないのが「実用性」と「芸術性」の両立です。
九谷焼・伊万里焼は、美術品でありながら器として使うことも可能です。
実際に食器や花瓶として使用することで、日常生活の中で芸術を味わえるのは大きな魅力です。
コレクターの中には、飾って楽しむだけでなく、特別な日には実際に使用する人も少なくありません。
コレクターが九谷焼や伊万里焼に魅了されるのは、
-
芸術的価値の高さ
-
歴史やストーリー性
-
希少性と資産価値
-
海外市場での評価
-
実用と美術の融合
といった要素が複合的に作用しているからです。単なる「古い器」ではなく、所有することで歴史や文化を手元に感じられる特別な存在。
それこそが、両者が時代を超えて愛され続ける理由なのです。
九谷焼の買取相場

九谷焼は、その華やかな色彩と芸術的なデザインから国内外で高い評価を受けています。
特に著名な作家の作品や、古い時代に制作された九谷焼は市場で高額査定されることも珍しくありません。
しかし一口に「九谷焼」と言っても種類や時代によって相場は大きく異なります。
ここでは、九谷焼の買取相場と査定のポイントを詳しく見ていきましょう。
作家物の相場
九谷焼の中でも特に高額で取引されるのは「作家物」です。
人間国宝や著名作家の作品はコレクター需要が高く、数十万円から数百万円の査定額がつくこともあります。
-
三代 徳田八十吉
九谷焼を代表する人間国宝。鮮やかな釉薬表現で知られ、花瓶や大皿は数十万〜100万円を超えるケースも。 -
吉田美統
金箔を使った加飾技法に優れ、現代九谷焼の名工とされる。作品は数万円〜50万円程度での買取実績あり。 -
宮本一夫・武腰潤ら現代作家
近代以降の作家も評価が高く、保存状態や作品の希少性によって10万円以上になる場合もある。
著名作家の作品は「共箱(作家署名入りの箱)」や「証明書」の有無が査定額に大きく影響するため、付属品を残しておくことが重要です。
古九谷・歴史的作品の相場
九谷焼の中でも「古九谷」と呼ばれる17世紀の初期作品は非常に希少で、美術館級の価値があります。
保存状態が良ければ数百万円を超える査定がつく場合もあります。
ただし古九谷は真贋の見極めが難しく、専門の鑑定が必要です。
本物であれば非常に高い価値がつきますが、模倣品や後年の作品は数万円〜数十万円程度にとどまることもあります。
一般的な九谷焼の相場
現代の九谷焼や量産された作品は、数千円〜数万円程度の査定が一般的です。
特にお土産用や日用品として流通したものは、美術的価値よりも実用性が重視されるため、高額査定は期待しにくい傾向にあります。
ただし、人気のあるデザインや未使用の状態で残っている場合、まとめて数万円になることもあります。
高額査定されやすいポイント
九谷焼を高く売るためには、以下の点が重視されます。
-
保存状態
欠けやヒビのない完品は高評価。使用感の少ないものほど有利。 -
付属品
共箱・栞・証明書が揃っていると査定額アップ。 -
サイズと存在感
大皿や大壺など大きな作品は希少で高額になりやすい。 -
人気作家
人間国宝や著名作家のサイン入り作品は別格の扱い。
九谷焼の市場動向
近年は国内外での需要が再び高まり、特に欧米市場では「ジャパン・クタニ」として人気が回復しています。
アート志向のインテリア需要が高まっており、鮮やかな色絵の九谷焼は「飾る美術品」として再評価されています。
そのため、過去には数万円程度だった作品が、現在では数十万円に跳ね上がるケースも見られます。
今後も市場価値が安定して推移する可能性が高いといえるでしょう。
九谷焼の買取相場は以下のように整理できます。
-
著名作家物
数十万〜100万円超 -
古九谷など歴史的作品
数百万円に達するケースも -
一般的な現代作品
数千円〜数万円程度
九谷焼を売却する際には、作家名や時代、保存状態をしっかり確認し、信頼できる鑑定士に依頼することが重要です。
思わぬ高額査定につながる可能性もありますので、まずは専門の査定に出すことをおすすめします。
伊万里焼の買取相場

伊万里焼は、日本で最初に誕生した磁器として歴史的価値が高く、国内外で根強い人気を誇ります。
特に「古伊万里」と呼ばれる江戸時代の作品はコレクター需要が強く、オークションや骨董市場でも高値で取引されています。
一方で、明治期以降に大量生産された伊万里焼や日用品としての器は相場が抑えめであるなど、作品によって評価が大きく分かれるのも特徴です。
ここでは、伊万里焼の買取相場を種類ごとに解説していきます。
古伊万里の相場
最も高額で取引されるのが「古伊万里」です。
17世紀から18世紀にかけて制作された作品で、初期伊万里や金襴手(きんらんで)などが特に高評価を受けます。
-
初期伊万里
白磁に素朴な藍色の染付を施した磁器。希少性が高く、保存状態の良いものは数十万円〜100万円を超えることも。 -
古伊万里染付
繊細な藍色文様が特徴で、皿や壺は数万円〜数十万円。大皿や希少なデザインはさらに高額。 -
古伊万里金襴手
赤絵や金彩を豪華に施したもの。数十万〜数百万円になることもあり、海外オークションでも注目される。
古伊万里は、ヨーロッパの貴族社会に影響を与えた歴史的背景から、国内外のコレクターが競って入手したがるジャンルです。そのため市場価値が安定して高く保たれています。
明治期〜近代伊万里の相場
明治以降は輸出需要に応えるため大量生産が行われました。
この時期の伊万里焼は装飾が豪華で華やかですが、現存数が多いため相場は比較的落ち着いています。
-
一般的な明治伊万里
数千円〜数万円程度。 -
豪華な装飾や大型作品
10万円を超えるケースもあるが、希少性や保存状態に左右される。
近代の伊万里焼は「美術品」としてよりも「骨董的インテリア」としての需要が強く、日常的に楽しめる価格帯で流通しています。
一般的な伊万里焼の相場
現代の伊万里焼や量産された日用品は、1点あたり数百円〜数千円程度の査定にとどまることもあります。
特に家庭用に普及した茶碗や小皿は高額にはなりにくい傾向です。
ただし、まとめ売りにすることで需要が生まれ、数万円単位の取引となる場合もあります。
高額査定につながるポイント
伊万里焼の査定で重要なのは、以下のような点です。
-
制作年代
江戸時代前期の古伊万里は特に高額。 -
保存状態
欠けやヒビのない完品は高評価。修復跡がある場合は減額される。 -
サイズと希少性
大皿や壺など大型作品は高額になりやすい。 -
デザイン・様式
金襴手や珍しい意匠は査定額アップにつながる。 -
由来や付属品
来歴が明確なものや、当時の箱や記録が残る品は評価が上がる。
市場動向と海外需要
伊万里焼は17世紀から国際的に流通していたため、現在でも海外需要が非常に強い陶磁器です。
特にヨーロッパのコレクター市場では「ジャパン・イマリ」としてブランド的価値が確立されており、オークションでは国内よりも高値がつく場合があります。
また、近年の和文化ブームにより、インテリアやアートとして伊万里焼を楽しむ層が拡大。市場価値は今後も安定して推移する可能性が高いといえます。
伊万里焼の買取相場は以下の通りです。
-
古伊万里(初期・染付・金襴手)
数十万〜数百万円 -
明治期以降の作品
数千円〜数十万円 -
一般的な現代伊万里
数百円〜数千円、まとめて数万円
伊万里焼は作品ごとの差が大きいため、査定時には必ず専門の鑑定士に依頼することが重要です。
希少な古伊万里や保存状態の良い作品をお持ちであれば、思わぬ高額査定が期待できるでしょう。
高く売るためのポイント

九谷焼や伊万里焼を売却する際、同じ焼き物でも査定額が大きく変わることがあります。
なぜなら、骨董品や美術品としての評価は「状態」「希少性」「付属品」など、複数の要素によって決まるからです。
ここでは、少しでも高く売却するためのポイントを詳しくご紹介します。
1. 保存状態を良く保つ
骨董品全般に共通しますが、保存状態は査定額に直結します。
-
欠けやヒビがないことは最低条件。
-
修復跡がある場合は減額対象。
-
使用感が少なく、彩色や金彩が鮮やかに残っていると高評価。
特に九谷焼は色絵が命、伊万里焼は白磁の美しさが命です。
色落ちや変色、ヒビ割れが少ないものほど価値が上がります。
2. 付属品を揃える
共箱(作家名や署名入りの木箱)、証明書、しおりなどが残っているかどうかは大きな査定ポイントです。
-
作家物の九谷焼
共箱があると査定額が2〜3割上がることも。 -
古伊万里
来歴を示す書付や保存状態の記録があれば信頼性が高まり、相場より高額査定されやすい。
売却を検討する際には、付属品を捨てずに大切に保管しておくことが重要です。
3. 人気作家や様式を確認する
作家名や時代様式が明確な作品は、それだけで価値が高まります。
-
九谷焼では「三代徳田八十吉」「吉田美統」など人間国宝クラスの作品は別格。
-
伊万里焼では「初期伊万里」「古伊万里金襴手」など、歴史的価値の高い様式が人気。
署名や刻印、特徴的な意匠を確認し、わからない場合は専門家に鑑定を依頼することをおすすめします。
4. 売却のタイミングを見極める
市場動向によって相場は変動します。近年は海外需要の高まりから、九谷焼・伊万里焼ともに高値傾向が続いています。
特に国際オークションの前後や、美術品市場が活発なシーズン(春・秋)は高額査定のチャンスです。
また、景気や為替の影響で海外バイヤーの購入意欲が強まる時期を狙うのも一つの戦略です。
5. 専門の買取業者を利用する
一般的なリサイクルショップやフリマアプリでは、九谷焼や伊万里焼の正しい価値を見極めてもらえないことがあります。
高額査定を狙うなら、骨董品・美術品に強い専門業者に依頼するのがベストです。
-
出張買取
大型の壺や皿などをまとめて査定してもらえる。 -
オークション代行
希少な作品なら国際市場に出品する方が高額になりやすい。
複数の業者に見積もりを依頼し、比較検討するのも効果的です。
6. 掃除や扱い方に注意する
売却前に無理に掃除をすると、かえって価値を落とすことがあります。
金彩や絵付け部分を強くこすると剥がれる可能性があるため、やわらかい布で軽く埃を払う程度が望ましいです。
専門知識のない状態で研磨や洗浄を試みるのは避けた方がよいでしょう。
九谷焼・伊万里焼を高く売るためには、以下の点を意識することが大切です。
-
保存状態を良く保つ
-
共箱や証明書など付属品を揃える
-
人気作家や様式を確認する
-
市場動向を見て売却タイミングを工夫する
-
骨董品専門の業者に査定を依頼する
これらを意識するだけで、数万円から数十万円、場合によっては数百万円もの差が出る可能性があります。
大切にしてきた作品を手放す際は、慎重に準備を整えて売却することが賢明です。
九谷焼・伊万里焼の今後の需要と市場動向

九谷焼と伊万里焼は、日本の陶磁器文化を代表する工芸品として長く評価されてきました。
近年では骨董ブームや和のライフスタイルの再評価により、その市場価値が再び注目を集めています。
ここでは、九谷焼・伊万里焼の需要が今後どのように変化していくのか、市場動向とともに考察します。
1. 国内市場の動向
日本国内では少子高齢化や住環境の変化により、骨董品全般の需要が落ち込む時期もありました。
しかし、ここ数年は「断捨離」や「終活」に伴い、買取市場に焼き物が多く出回るようになった一方、若い世代がインテリアやアートとして再評価する動きも見られます。
-
九谷焼は「色絵の華やかさ」がモダンなインテリアに映えるとして人気。
-
伊万里焼は「シンプルで上品な染付」が和洋問わず空間に取り入れやすく、実用と装飾を兼ねた需要が高まっている。
国内市場は一見飽和しているように見えますが、デザイン性や作家物に注目が集まり、選別された需要が続くと予想されます。
2. 海外市場の拡大
今後の市場を語る上で外せないのが海外需要です。
欧米ではすでに「ジャパン・クタニ」「ジャパン・イマリ」として古くから評価されており、美術館やコレクターの所蔵品も数多く存在します。
近年はアジア市場でも日本の伝統工芸品が人気を集め、特に中国や台湾、韓国の富裕層が積極的に購入している傾向があります。
オークションでは伊万里焼の大皿や古九谷の壺が高額で落札される事例も増え、国内価格より海外の方が高値で取引されるケースも目立ちます。
3. 作家物・人間国宝作品の安定した需要
市場全体の需要が変動する中でも、作家物や人間国宝の作品は安定して高額で取引されています。
-
九谷焼の徳田八十吉、吉田美統といった巨匠の作品は今後も価値が下がりにくい。
-
伊万里焼では「古伊万里金襴手」といった歴史的な様式が引き続き高額落札対象。
美術的価値が確立された作品は景気に左右されにくく、長期的に安定した需要が続くと考えられます。
4. 新しい需要の形
現代では、従来の「コレクションとして飾る」だけでなく、日常生活に取り入れる動きも出ています。
-
九谷焼のカップや小皿をモダンな食卓に合わせる。
-
伊万里焼の大皿をアートピースとして壁に掛ける。
また、SNSやECサイトの普及により、若い層が気軽に購入できるようになり、市場が広がりつつあります。
特に海外バイヤーに向けたネット販売は、これからさらに拡大する可能性が高いでしょう。
5. 今後の市場予測
今後10年を見据えると、九谷焼・伊万里焼の市場は「二極化」していくと予想されます。
-
一般的な日用品的な作品 → 相場は安定もしくはやや下降傾向。
-
古伊万里・古九谷・著名作家物 → 希少性が高まり、さらに高額取引が進む。
国内では需要が一巡する可能性がありますが、海外需要がそれを補う形で全体的な市場価値を押し上げていくと考えられます。
九谷焼・伊万里焼の今後の需要と市場動向を整理すると以下の通りです。
-
国内ではアート・インテリア需要が堅調。
-
海外では富裕層を中心に需要拡大。
-
作家物や古作は引き続き高額査定。
-
日用品的な作品は相場が安定もしくは横ばい。
市場は変化しつつも、芸術性・歴史性を備えた九谷焼と伊万里焼は、今後も日本を代表する陶磁器として確かな価値を保ち続けるでしょう。
九谷焼・伊万里焼の価値を理解して賢く売却

九谷焼と伊万里焼は、いずれも日本を代表する陶磁器であり、芸術的価値と歴史的背景を兼ね備えています。
九谷焼は色彩の鮮やかさと装飾性で魅了し、伊万里焼は磁器としての完成度と国際的な影響力で世界に名を馳せてきました。
両者は日本文化を象徴する存在でありながら、その価値は今もなお進化し続けています。
九谷焼・伊万里焼の価値を改めて整理
-
九谷焼
豪華絢爛な色絵磁器。古九谷から現代作家物まで幅広い魅力を持ち、作家物や大作は数十万〜数百万円に達することもある。 -
伊万里焼
日本初の磁器。初期伊万里や古伊万里金襴手は特に希少で、国内外のコレクターが高額で取引。
両者ともに、保存状態・付属品・作家名・制作年代によって査定額が大きく変わります。
賢く売却するためのポイント
これまでの章で解説してきた通り、高く売却するためには以下の点が重要です。
-
保存状態を良く保つ
欠けやヒビのない完品は高評価。色絵や金彩が鮮やかに残っているとさらに有利。 -
付属品を揃える
共箱・証明書・来歴を示す資料は必ず保管しておく。 -
作家や様式を把握する
人間国宝や著名作家、古伊万里・古九谷といった歴史的価値ある作品は高額査定の対象。 -
市場動向を見極める
海外需要が高まっている今は売却の好機。特に国際オークションの動きに注目。 -
専門業者に依頼する
骨董品に精通した鑑定士や業者に査定を依頼することで、本来の価値を見逃さずに済む。
今後の市場を踏まえて
近年、九谷焼・伊万里焼は海外での需要が高まっており、特に欧米やアジアの富裕層からの人気が強い状況です。
国内市場でも若い世代がインテリアやアートとして購入する動きが見られ、今後も一定の需要が続くと予想されます。
ただし、市場は二極化が進んでおり、一般的な日用品的作品は相場が落ち着く一方、希少な古作や作家物はさらに価値が高まる傾向があります。
売却を考える際は、自分の持っている作品がどちらに当たるのかを見極めることが重要です。
まとめの言葉
九谷焼と伊万里焼は、単なる焼き物ではなく、日本の歴史と文化を映し出す芸術作品です。
手元にある一品が、思わぬ高額査定につながる可能性もあります。
もし売却を検討しているなら、まずは専門の鑑定士に相談し、価値を正しく見極めることから始めましょう。
「受け継がれてきた工芸品を未来へとつなぐ」― その第一歩が、賢い売却の判断です。
九谷焼、伊万里焼の出張買取は高価買取専門店【戎ノ蔵】にお任せください
引用元:【戎ノ蔵】公式サイト
大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・福井で九谷焼、伊万里焼の出張買取は高価買取専門店【戎ノ蔵】にお任せください!1件1件丁寧に、経験と知識が豊富な査定士の確かな目利きで、価値ある品を見極め高価買取いたします。戎ノ蔵なら状態の悪いモノ、他店で買取不可とされてしまったモノでも買取いたします。出張費は完全無料のため、まずはお気軽にお問合せください。